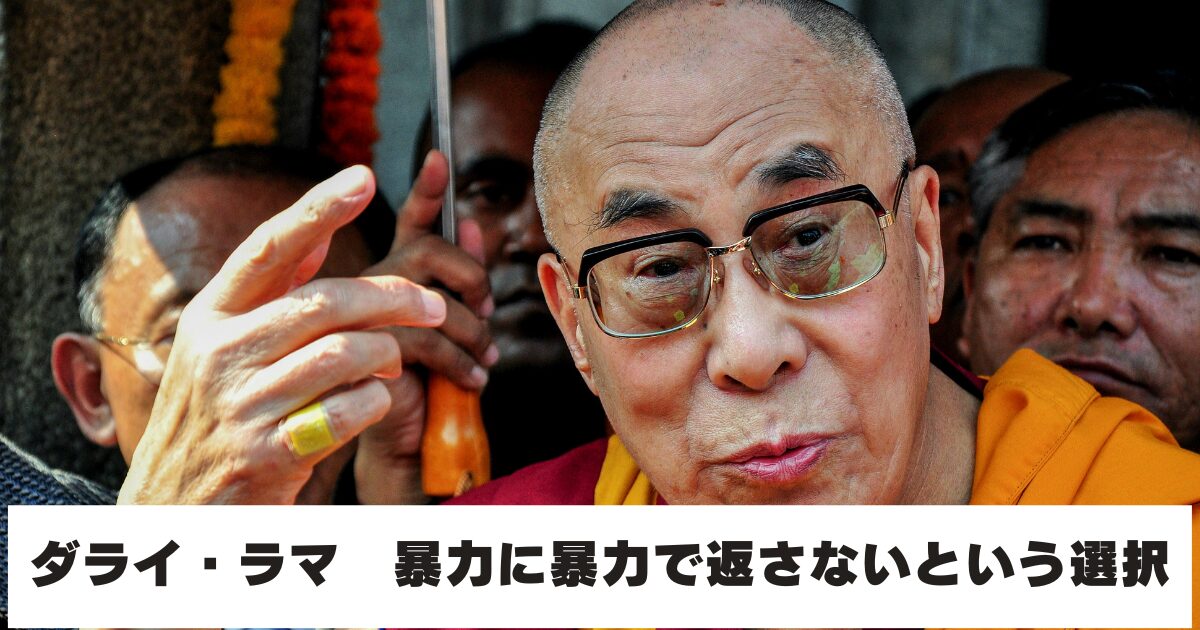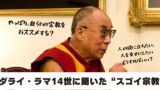怒りを向けられたとき、私たちはどう反応するでしょうか。言い返す、拒む、距離を置く——。
でも、もしその瞬間に“愛で返す”ことを選べたなら、そこに生まれるのは、まったく違う未来かもしれません。
ダライ・ラマ14世が生涯を通して示してきたのは、まさにその「非暴力」という生き方です。
それは理想論ではなく、魂の成熟を映し出す姿勢。暴力に暴力で返さないという選択です。宗教や国境を超えて、人間としての本当の強さと優しさを教えてくれます。
ニューヨークで出会ったチベット人たち

20代の頃、私はニューヨークに滞在していました。その時に出会ったチベット人の青年が、映画『セブン・イヤーズ・イン・チベット』のエキストラをしていたんです。「ブラッド・ピットと一緒に出たんだ」と、少し照れながら見せてくれた写真。その笑顔の奥に、故郷を追われた人の深い悲しみが見えた気がしました。
彼のチベット人の友人から、忘れられない話を聞いたことがあります。彼はある権力者からダライ・ラマの写真を踏むように強要されたそうです。「もし踏まなければ殴る」と脅されても、
彼はその写真を見つめたまま、静かに涙を流したと話してくれました。
彼の瞳には、怒りではなく、深い祈りが宿っていました。どれだけ痛みを受けても、ダライ・ラマは決して暴力で返さない。「敵にさえ慈悲を向ける」というその姿勢は、聞いている私の心を深く揺さぶりました。
彼らの誘いで、ワシントンD.C.で行われたダライ・ラマの講演に参加しました。その帰り、ワシントンD.C.からニューヨークまで、ニューヨークのチベット人たちの貸し切りバスに乗せてもらいました。その車中で、チベット人たちは故郷の歌を合唱しはじめたのです。最初は明るく響いていた歌声が、次第にすすり泣きに変わり、バスの中は静かな祈りの場のようになっていきました。
私はその光景を忘れられません。国を追われながらも、彼らは怒りではなく慈悲と誇りを持っていたのです。
ダライ・ラマが語る“輪廻転生”とカルマの循環

2025年、ダライ・ラマ14世は亡命先のインドで声明を発表し、自身の死後も「輪廻転生(りんねてんしょう)」の制度を続ける意向を示しました。「新たなダライ・ラマは、自由世界から生まれるだろう」と語り、次の世代へと“魂のバトン”を渡す姿勢を見せています。
中国政府はこれに強く反発し、「転生は国家の承認が必要」と主張。それでもダライ・ラマは、政治ではなく魂の自由を選び続けている。
このニュースを聞いたとき、私はチベット人の友人たちの涙声を思い出しました。彼らの祈りは、世代を超えて今も息づいている——。「輪廻転生」とは、単に“生まれ変わる”ことではなく、慈悲を次の時代へと受け継ぐというカルマの昇華なのかもしれません。
チベットにも“カルマ”があるという視点

ダライ・ラマは、現在のチベットの苦難を「怒りではなく理解から見つめるべき」と語っています。
チベットは長い歴史の中で、平和な時代もあれば、他国との争いや支配関係を持った時期もありました。そうした過去を隠さず見つめながら、「私たちの経験には意味がある」と受け止める姿勢を示しています。
つまり、今の苦難を“罰”ではなく“学びの機会”としてとらえるのです。カルマ(業)とは、宇宙の“因果の学び”のようなもの。過去に与えた痛みを、今度は自らが受け取ることで、魂は「痛みの向こうにある慈しみ」を知っていく。
怒りを繰り返すか、理解に変えるか。その選択が、カルマを続けるか、超えていくかの分かれ道なのだと思います。
カルマを超える方法とは
カルマの本質は、“反応の連鎖”にあります。怒りに怒りで返せば、同じエネルギーがまた生まれる。でも、愛で返すと、その瞬間に鎖がほどける。
ダライ・ラマの生き方は、まさにこの「エネルギーの置き換え」。外側を変えるよりも、自分の内側の反応を変えること。それが、カルマの連鎖を止める最も確かな方法です。
「許すことは、負けることではなく、自由になること。」その言葉を、私は彼の生き方そのものから学びました。
私たちにできる“愛で返す”小さな実践
カルマを超える道は、特別な修行ではなく、日常の中にたくさんのヒントがあります。
・嫌味を言われたとき、あえて穏やかに返す
・理不尽な言葉に、沈黙で応える
・誰かの悪意を感じたとき、心の中で「あなたが幸せでありますように」と祈る
小さなことのように見えて、それが“愛で返す”第一歩です。そしてそれは、誰かのカルマをも癒す行為でもあります。
終わりに:カルマの輪を愛で閉じる
チベットの痛みも、個人の痛みも、暴力では終わらせず、愛で閉じることで新しい始まりになります。ダライ・ラマが体現しているのは“赦し”よりも“理解”。カルマを超えるとは、過去の痛みを学びに変えること。
あの日、バスの中で涙声になりながら歌っていた彼らの祈りが、いまも静かに世界に響いている気がします。
「許しとは、相手を赦すことではなく、自分を自由にすること。」
私たちもまた、日々の中で、小さな“愛で返す”選択を積み重ねていけたらと思います。